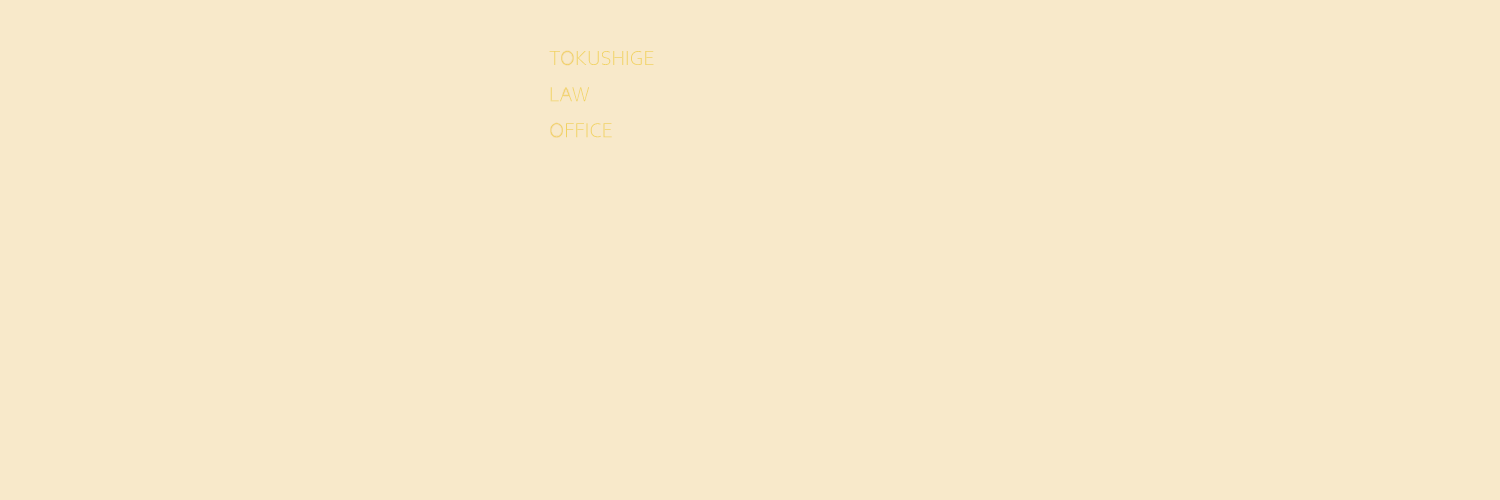当事務所で扱った次の事例は、脳動脈瘤破裂によりくも膜下出血を発症して死亡した女性C(当時43歳)の遺族が、労災(過労死)を認めなかった労働基準監督署に対し、認定の取り消しを求めて提訴した事案です。
発症前6か月間の残業時間は月平均65時間程度で、過労死ラインとされる80時間には達していませんでした。しかし、詳しく見ていくと、発症前4~6か月の残業時間は1か月あたり86時間~126時間以上と、過労死ラインを大きく上回っており、仮に発症が1~2か月早かった場合は、過労死と認定される可能性が非常に高い事案でした。
ところが第一審は、Cの死亡前1~3か月の残業時間が7~36時間程度で推移しており、この間のCの睡眠時間が慢性的に短い(Cは毎月提出する健康診断問診票に睡眠時間が5時間程度であると記入していた)のは、私的リスクファクター(要するにCの自己責任)であり、これにより脳動脈瘤が悪化した可能性があるなどとして、過労死とは認めませんでした。
しかし、脳動脈瘤はいったんできてしまったら自然に消失することはありません。本件でも、発症前4~6か月の過労死ラインを大きく上回る残業等により脳動脈瘤が発生し、またはもともとあった脳動脈瘤を悪化させるなどの影響を与えた可能性は非常に高く、その影響が2~3か月で無くなることはありえないわけですから、睡眠時間が慢性的に短かったという事情があったとしても、過労死ラインを大きく上回る残業等の影響を全く無視した第一審の判断は不当であると言わざるを得ませんでした。
我々は控訴を申し立てるとともに、第一審の判断がいかに不当であるかを詳細に主張しました。その結果、高裁では逆転勝訴し、無事過労死であるとの認定を得ることができました。
高松高裁令和2年4月9日判決(令和元年(行コ)第20号 遺族補償給付等不支給処分取消請求控訴事件)
主文
1 原判決を取り消す。
2 高松労働基準監督署長がBに対して平成28年2月19日付けでした労働者災害補償保険法による遺族補償給付及び葬祭料を支給しない旨の各処分を取り消す。
3 訴訟費用は,第1・2審とも被控訴人の負担とする。
事実及び理由
(中略)
被控訴人は,Cの業務外のリスクファクターとして,Cの睡眠時間は,業務量の多寡にかかわらず5時間程度であった旨主張する。
前記認定のとおり,専門検討会において,1日5時間以下の睡眠は,脳・心臓疾患の発症との関連性において有意性がある旨指摘されている。
そして,前記認定のとおり,Cは,平成26年5月29日付け,同年7月8日付け,同年7月31日付け,同年8月29日付け,同年9月26日付け及び同年11月4日付けの健康診断問診票に,いずれも睡眠時間が1日約5時間である旨記載している。
しかしながら,Cの時間外労働時間は,平成26年5月29日を含む発症前6か月目には86時間30分であり,その労働時間の長さから,睡眠時間が5時間程度にならざるを得ない状態になっていたと認められる。また,同年7月8日を含む発症前5か月目も時間外労働時間が107時間8分と10時間を超えており,その労働時間の長さから,5時間程度の睡眠時間を確保することも難しいほどになっていた。さらに,同年7月31日を含む発症前4か月目(同年7月25日から同年8月23日まで)も時間外労働時間が126時間33分であり,5時間程度の睡眠時間を確保することも難しい状態であった。同年8月29日を含む発症前3か月目(同年8月24日から同年9月22日まで)の時間外労働時間は35時間57分ではあるが,その前の1か月間の時間外労働時間が126時間33分であり,同年8月29日は発症前4か月目が終わって6日目であるから,同時点においても,睡眠時間が1日5時間程度というのは,それまでの1か月間の労働時間の長さからして不自然ではなく,むしろ,いまだ1日5時間の睡眠時間を確保するのが困難であった時期であるといえる。このように,平成26年5月29日付け,同年7月8日付け,同年7月31日付け,同年8月29日付けの健康診断問診票の記載は,労働時間の長さから,実際に睡眠時間が5時間程度であったか,5時間にも満たないような時期に記載されたものと認められる。
同年9月26日を含む発症前2か月目の時間外労働時間は7時間36分で,その前の1か月も時間外労働時間が35時間57分であるから,労働時間だけでいえば,Cは,1日7時間半以上の睡眠時間を確保できる状態にあったといえる。同年11月4日を含む発症前1か月目も時間外労働時間は29時間13分であるから,労働時間だけでいえば,Cは,1日7時間半以上の睡眠時間を確保できる状態にあったといえる。それにもかかわらず,Cが,平成26年9月26日付け及び同年11月4日付けの健康診断問診票に睡眠時間が1日5時間程度である旨記載しており,それを正確な記載と考えれば,Cは,労働時間の長短にかかわらず,睡眠時間が1日5時間程度と短かったものという見方もできないわけではない。
しかしながら,上記各健康診断問診票に記載された睡眠時間が正確なものであることの保証は何らなく,以前の問診票の記載が5時間になっていたことから,単にそれを踏襲して,5時間と記載した可能性も否定できず,いずれにしても,問診票の睡眠時間の記載のみから,Cの睡眠時間が業務の多寡にかかわらず,5時間であったなどとは到底認められないというべきである。
したがって,問診票記載の睡眠時間が約5時間であるということが,私的なリスクファクターになるとは認められない。
他に,Cのくも膜下出血と関連性のある業務以外のリスクファクターを認めるに足りる的確な証拠はない。
(4) 業務起因性についての総合判断
以上の事情を総合して,認定基準を参照して,本件における業務と発症との関連性について判断する。
前記認定のとおり,Cの時間外労働時間は,発症前6か月間の1月当たりの平均が65時間29分と45時間をはるかに超える長時間ではあるが,認定基準において業務と発症との関連性が強いとされる80時間には達していない。
しかしながら,発症前6か月目は86時間30分,発症前5か月目は107時間8分,発症前4か月目は126時間33分といずれも80時間を超えるものであり,この時期については,Cの業務は,時間外労働時間の長さの点だけをとっても,過重なものであったことは明らかである。
しかも,前記認定のとおり,Cは,時間外労働時間が長いばかりではなく,発症前6か月の約2か月前である平成26年4月に平社員から情報部門のリーダーになってより責任の重い立場になるという人事異動があった上,同年8月には本件大型案件を含む2件の入札案件で敗退し,平成26年度下期の売上げノルマ達成が極めて困難になるなど,過大なノルマがある業務に従事していたものであり,精神的にも強い緊張状態にあったものと推認できる。したがって,この時期のCは,時間外労働時間が長いことに加えて,精神的緊張を伴う過大なノルマの達成をチームリーダーという責任ある立場で遂行していたものであり,その精神的負荷は極めて高く,疲労の蓄積が極めて著しかったものと推認できる。
そして,発症前3か月目以降(平成26年8月24日以降)は,時間外労働時間こそ月45時間を下回る状態が続いていたが,ノルマ達成が極めて困難な状態である平成26年度下期の直前から平成26年度下期の開始2か月間くらいの時期であり,チームリーダーとして過大なノルマの達成の責任を負うという精神的緊張を伴う業務に従事するという状態に変わりはない。しかも,本件疾病の発症の約1か月前である平成26年10月24日には労働災害で右大腿部挫傷,仙骨骨折という大きな怪我をしたことにより,痛みに耐えながら業務に従事しなければならなくなり,Cの業務における精神的緊張はより一層高まったものといえるのであり,時間外労働時間が短くなったことにより疲労が回復するどころか,精神的緊張を伴う業務により更に疲労を蓄積させていったものと推認できる。
他方,Cは,喫煙をせず,多量の飲酒もせず,脳・心臓疾患と関連の深い既往歴はなく,Cの家族にも脳・心臓疾患の既往歴はなく,高血圧でもなく,業務以外に脳動脈瘤破裂によるくも膜下出血を発症させるようなリスクファクターは認められない。
このように,Cの業務が,発症前6か月目から発症前4か月目までは,時間外労働時間も極めて長く,業務も精神的緊張を伴うものであったこと,発症前3か月目以降は時間外労働時間が短くなったものの,精神的緊張を伴う業務であることには変わりがない上に,労働災害により大きな怪我までしたこと,他方において,業務以外のリスクファクターが認められないことからすれば,Cは,発症前6か月目から発症前4か月目にかけての毎月80時間を超える極めて長時間の時間外労働に加え,精神的緊張を伴う業務により疲労が著しく蓄積され,時間外労働時間が比較的短くなった発症前3か月目以降も,精神的緊張を伴う業務が続いたことにより蓄積した疲労が回復するどころか,かえって,精神的緊張を伴う業務により更に疲労を蓄積させ,本件疾病を発症したものと認めるのが相当である。
そうすると,認定基準そのものに直ちに該当しないとしても,それだけで,労働基準法施行規則35別表第1の2第8号に当たらないと直ちにいえるものではなく,専門検討会報告書が指摘する労働時間,勤務形態,作業環境,精神的緊張の状態等に照らして,Cの業務と本件疾病の発症との間には相当因果関係(業務起因性)が認められるというべきである。
(以下略)
(原審)
高松地裁令和元年5月31日判決(平成28年(行ウ)第14号 遺族補償給付等不支給処分取消請求事件)
主文
1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
(中略)
(ア) 原告は,業務起因性の判断にあたっては,血管病変の不可逆性などを十分に考慮すべきである旨主張する。
血管病変の不可逆性については,前記3(2)ウ(イ)のとおり,医学的にも議論の余地があるとされている。もっとも,血管内の力学的負荷により,血管内膜の内弾性板,中膜平滑筋層が断裂,消滅し,血管外膜に直接血圧が加わることで,外膜が瘤状に変形するという脳動脈瘤の形成過程からすれば,一度生じた脳動脈瘤は,疲労が回復しても改善されないということは十分考えられるから,脳動脈瘤に限っていえば,血管病変の不可逆性というものには合理的根拠があるように見える。
そして,脳動脈瘤破裂による可能性が最も高いと考えられる本件においては,かかる血管病変の不可逆性を前提に,一定期間の過重労働により,脳動脈瘤が破裂寸前の状態になったことが客観的に認められる場合には,その後の発症までの間の労働が過重労働であると評価されないとしても,当該過重労働の影響が発症時まで残存し,その発症をもたらしたとみる余地は一概には否定できない。
(イ) 認定基準では,発症前1か月間におおむね100時間又は発症前2か月ないし6か月間にわたって,1か月当たりおおむね80時間を超える時間外労働が認められる場合,業務と発症との関連性が強いと評価されているところ,Cの時間外労働時間数は,発症前6か月は80時間を上回り,発症前4か月及び5か月は100時間を上回っており,かかる期間のCの業務は,労働時間の観点からみると過重なものであったといえる。しかし,脳血管疾患は複数の要因により増悪するものであり,特に,発症前1か月から3か月は業務の過重性が認められない状況にあったにもかかわらず,慢性的に睡眠時間が短かったという私的リスクファクターと評価すべき事情があり,これにより脳動脈瘤が悪化した可能性があることも踏まえて検討すると,発症前4か月ないし6か月の労働時間数のみをもって,発症前4か月の時点において,Cの脳動脈瘤が破裂寸前の状態にあったと認めることはできない。
したがって,Cについて,発症前4か月から6か月の間の過重労働の影響が本件疾病の発症時まで残存し,その発症をもたらしたと認めることはできない。
エ まとめ
以上の検討によれば,本件会社においてCが従事した業務が,認定基準を満たすような過重な業務であったとは認められず,その他,原告が主張する事実を踏まえても,Cが従事した業務が過重であり,それにより血管病変等を自然経過を超えて著しく増悪させ,本件疾病を発症したとは認められないから,本件疾病と業務との間に相当因果関係は認められない。
(以下略)